こんにちは~病院薬剤師のMoKaです。
病院薬剤師として働き始め毎日調剤や監査に追われて、ふと「これって単なる作業じゃないか…?」と不安になること、ありませんか?
正確に仕事をこなしていても、どこか達成感が薄かったり、「評価されてるのかな?」と自信が持てなかったり。そんなモヤモヤ、実は誰もが一度は通る道です。
私自身も新人時代、調剤業務を“作業”としてこなすだけで終わっていた時期がありました。けれどある時、先輩のひとことをきっかけに、「作業」と「仕事」の違いに気づき、日々の業務の見方が少しずつ変わっていきました。
この記事では、
- 「作業」と「仕事」の本質的な違い
- 作業を“仕事”に変えるための5つの視点
- さらに成長したい人へ。おすすめの3冊
を分かりやすくお伝えします。
調剤業務は、ただの作業じゃない
そもそも、「作業」と「仕事」の違いって何でしょうか?
私が感じたのは、
- 作業=言われたことを、そのまま正確にやること
- 仕事=目的や意味を考えて、自分なりに価値を生み出すこと
です。
たとえば、
「この薬、患者さんにとって本当にベストな選択なのか?」
と、ほんの少しでも考えながら調剤する。
それだけで、作業から仕事に変わるんだと気づきました。
作業を“仕事”に変えるための5つの視点
1. この処方、本当に問題ない?と一歩立ち止まってみる
処方された薬が絶対に正しいとは限りません。
用量用法、重複、相互作用、副作用リスクをパッと見て確認。
「何かおかしくないか?」という視点を持つことが仕事です。
2. 患者背景まで考えてみる
処方せんは紙です。
ですが、処方せんに書いている薬を使うのは人(=患者さん)。
患者さんの年齢、腎機能、体重、妊娠、食事状況などを意識することはとても重要です。
患者さんの背景を知ると、調剤が“意味ある行動”に変わります。
3. 「このやり方、もっと良くできないか?」と考える
調剤の仕方も一通りではありません。
調剤台の配置、印刷設定、ラベル貼付など、小さな改善でもOK。
小さなことでも改善することで、もっと良い方法に変わるかもしれません。
改善提案ができる人は“作業者”ではなく“貢献者”に見られます。
4. 小さなミスを自分ごととして振り返る
人はミスをします。
自分のミスは自分ごととして考えると思いますが、他人のミスはどうでしょうか?
他人のミスだから関係ないではありません。
他人のミスでも「自分ならどう防ぐ?」と考えるクセをつけてみましょう。
再発防止に関われる=仕事人の第一歩です。
5. チームで動く意識を持つ
調剤室は個人プレーではなくチームで回していく場所です。
自分の仕事だけに集中するのではなく、「次に誰が何をするのか」「誰が困っていそうか」といった周囲の状況に目を向けながら動けるかどうかが重要です。
たとえば、指導薬剤師が処方鑑査に追われているなら、「お手伝いできることありますか?」と声をかけてみる。
あるいは、患者対応が同時に重なったときにさっと役割を調整する。
そんなちょっとした気配りや行動が、チーム全体のスムーズな業務に直結します。
そして何より周囲を見て動ける人は、自然と信頼される存在になっていきます。
チームで動いているという意識を持ちましょう。
新人時代こそ、小さな意識が未来を変える
薬剤師の仕事は、薬を渡すだけじゃありません。
患者さんの生活を支える、大事な役割があります。
新人のうちは「とにかくミスしないこと」に必死で、それ以外のことに目を向ける余裕がないかもしれません。
でも、大丈夫。
焦らなくていいし、完璧を目指さなくていい。
ちょっとずつ、意識を積み重ねれば、必ず「信頼される薬剤師」へ成長できます。
私もまだまだ学びながらの毎日です。
一緒に、"作業"から"仕事"への一歩を踏み出していきましょう!
さらに成長したい人へ。おすすめの3冊
もし、「もう一歩成長したい」「仕事の質を上げたい」と思ったときは、書籍の力を借りるのもおすすめです。
以下は私自身が助けられた本たちです。
『新薬情報オフライン』
薬剤師として知っておきたい新薬の基礎知識、作用機序、類薬との比較、処方監査、服薬指導のポイントなどを網羅掲載しています。
『エッセンシャル思考』
「やるべきこと」に集中するための思考法。薬剤師にも有効です。
『入社1年目の教科書』
医療職でも通用する“社会人の基本”。人との関わりや動き方を見直せます。
作業から仕事へ── それは、ほんの少しの視点の違いから始まります。
今日からできる小さな意識改革で、未来の自分の価値が変わるかもしれません。
本記事を最後まで読んでくださりありがとうございました。
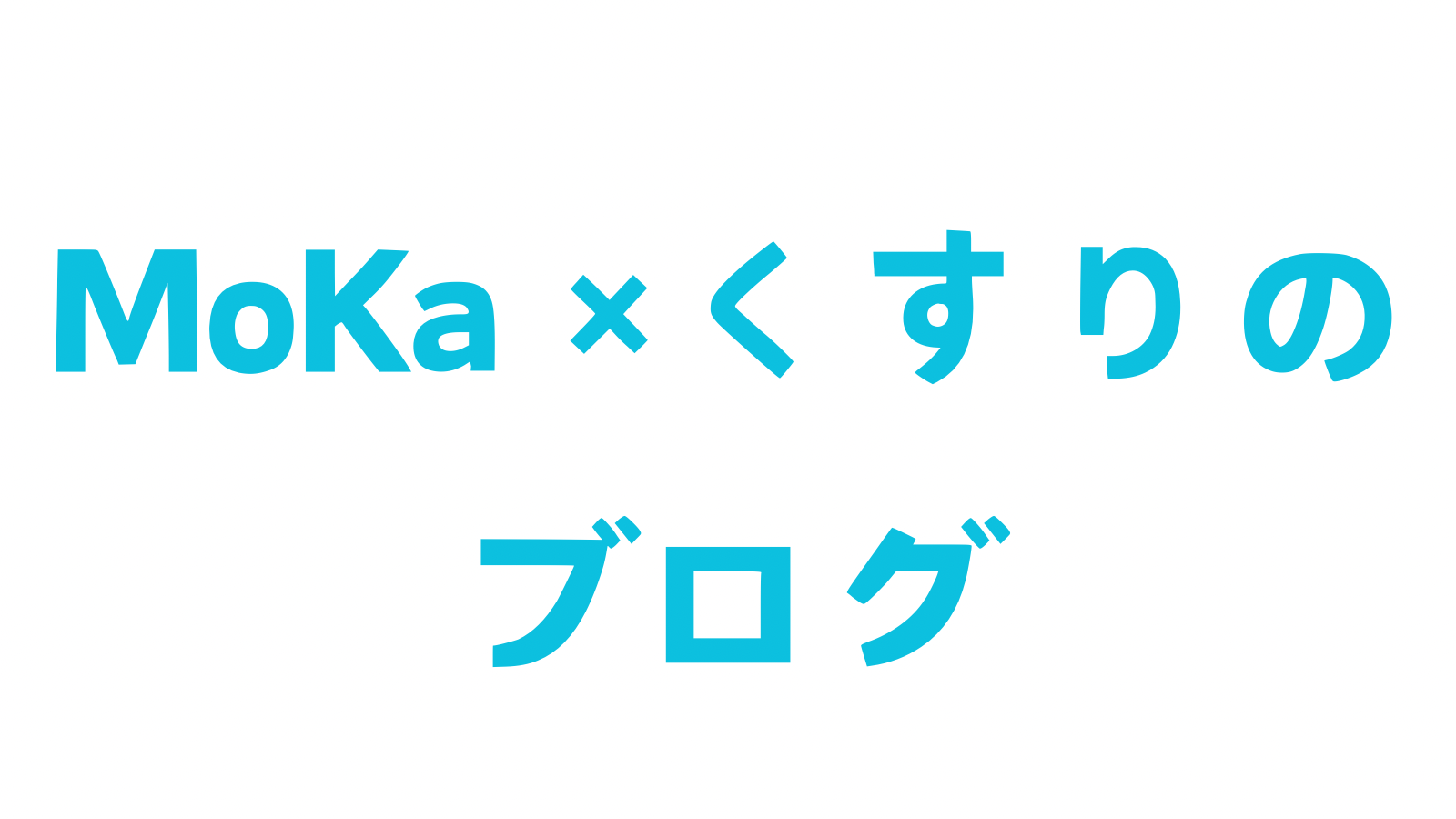

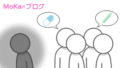
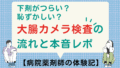
コメント